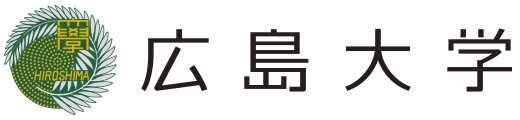
Emergency and Critical Care Medicine救急集中治療医学
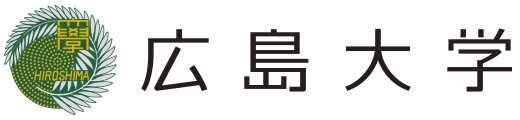
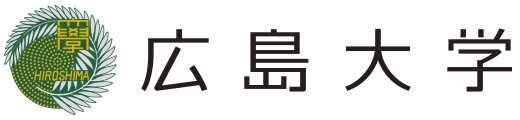
Emergency and Critical Care Medicine救急集中治療医学
ECMO Simulation
ECMO(体外式膜型人工肺)は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックで広く知られるようになった医療機器です。重症呼吸不全の患者さんに対し、血液を体外で酸素化し、二酸化炭素を除去することで、肺の機能を助ける役割を果たします。血液透析に似た原理ですが、1分間に全身の血液がすべて入れ替わるほどの高流量で血液を循環させるという点が異なります。さらに、この管理を数週間継続する必要があり、その間にさまざまな合併症やトラブルが発生する可能性があるため、安全かつ適切な運用には高度な技術と経験が求められます。そのため、ECMOを効果的に使用するためには、医療スタッフが繰り返しトレーニングを行い、管理技術を磨くことが不可欠です。

広島大学は、2009年のH1N1インフルエンザ・パンデミック時からECMOの有効活用に取り組んできました。現在では、広島県内の多くの救命センター・集中治療室(ICU)と連携し、重症呼吸不全患者さんの集約化を進めています。集約化により、患者さんの生存率がさらに向上することが明らかになっています。COVID-19パンデミック時には、広島県内のECMO管理が必要な患者さんを広島大学に集約し、迅速かつ適切な治療を提供しました。この取り組みは、今後の感染症流行時にも大きな意義を持つ可能性があると考えています。

広島大学では、ECMOの普及と技術向上を目的とした講習会やシミュレーション教育を、2012年から国内外で積極的に展開しています。COVID-19流行時には、NPO法人日本ECMOnetを設立し、国内の複数施設と協力しながらECMO教育を推進。中四国地方を中心に、全国47都道府県すべてで講習会を実施しました。
また、ECMOを適切に活用するためには、最新の人工呼吸管理に関する知識が不可欠です。そのため、人工呼吸器の運用に関する最先端の知見を取り入れた講習会やハンズオンセミナーも開催し、ECMOと人工呼吸の適切な併用管理について指導を行っています。
講習では、座学だけでなく、実際の人工呼吸器やECMO機器を使用し、ブタ肺や高性能シミュレーターを用いた実習を通じて、チューブの切断や回路の組み立てなど、実践的なトレーニングを提供しています。これにより、受講者が実際の医療現場で即座に対応できるスキルを身につけることを目指しています。

広島大学のECMO教育は国内にとどまらず、アジア太平洋ECMO学会(APELSO)と連携し、ECPR(ECMOを用いた心肺蘇生)シミュレーションの指導も行っています。心肺停止は病院内外を問わず発生し、呼吸ECMOと比べてより迅速な対応が求められるため、どの場所で、どの順序で、どの機器を用いて蘇生を行うかを適切に判断する能力が必要とされます。
例えば、ECPRシミュレーションでは、マラソン大会中に心肺停止患者さんが発生したという想定のもと、発生現場で心肺蘇生とECMOを開始し、病院へ搬送するまでの一連の流れを訓練しました。こうした実践的な訓練により、迅速な判断と適切な対応を可能にする医療チームの育成に貢献しています。

COVID-19流行は収束しましたが、今後も新興・再興感染症の大流行による多数の重症呼吸不全患者さんが発生する可能性があります。その際に迅速かつ的確な医療を提供できるよう、私たちは日々トレーニングを重ねながら、少しでもより良い医療を提供できるよう努力を続けています。
広島大学の救急集中治療医学教室は、ECMOを含む重症患者さんの管理に取り組み、国内外の医療現場で活躍する人材を育成しています。常に最新の知識と技術を学びながら、医療現場で役立つスキルを高めていくことを目指しています。私たちとともに、最先端の救急集中治療を学び、未来の医療を支える仲間が集まってくれると嬉しいです。